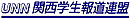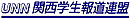ボランティアのコーディネートを
神戸大総合ボランティアセンター |
「微力ながら何かできることはないか」と全国から駆けつけた学生は地元の住民とともに、さまざまな分野で活躍した。被災地での「ボランティア活動」は地域の中で学生が多様な役割を果たし得るという可能性を示したといえる。
被災地に建つ神戸大でも多くの学生がボランティアに参加したが、授業が始まり学生が引き上げ始めると、学内からボランティアの統一窓口を望む声が多くあがった。こうして95年5月、当時大学では珍しいボランティアのコーディネイト機関「神戸大学総合ボランティアセンター」(以下総ボラと略す)が設立された。 |
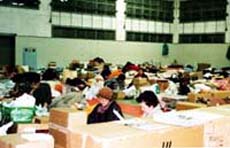
避難所となった震災直後の神戸大(95年1月27日) |
●4人からのスタート〜総合ボランティアセンターの歩み
発起人4人から始まった総ボラの当初の目的は、震災で活動した学生ボランティアに今後も情報ときっかけを与えることだった。当時の副代表、藤室玲治さん(現博士課程2年)は「被災地において彼ら(ボランティア)が直面し解決しようとした問題はふだんからも地域社会に存在する。被災地で示されたボランティアの可能性を次代に伝えられないまま、震災救援で活躍したボランティアが消散してしまうことだけは防がなければならなかった」と当時を振り返る。
総ボラは会員登録制で、ニーズに対して希望者のローテーションを組むという方式をとっている。登録者は7月には40人、翌年には100人を超え仮設住宅、児童館、福祉施設などのセクションに分かれ本格的な活動が始まった。
設立から7年がたった今、震災の枠から離れ、ボランティアの輪はさまざまな分野に広がった。「福祉以外の分野にも活動の幅を広げていきたい」と話すのは現代表の魚川大輔さん(経営・3年)。これからは地域とコミュニケーションを取ることのできる集団を作っていきたいという。
●「生涯のテーマに出会えた」
設立から2年間、総ボラで活動をした藤室さんは「震災の時は高齢者、障害者、在日の被災者が多くいてまさに社会問題の縮図だった。その中で学ぶことも多かった」と話す。しかしその一方で下に伝える難しさを強く感じている。「震災の時はあれだけ(ボランティア)が盛んだったけど、その中で本当に教訓をいかせたかなあ。いろんな人に関わってほしいという気持ちはあるけど、ボランティアの可能性を下に伝えきれかったんじゃないか」
藤室さんは現在、総合人間科学研究科の博士課程で学びながら、高齢者用の仮設住宅「グループハウス尼崎」(現在は恒久住宅)で働いている。「ボランティア活動を通して生涯のテーマに出会えた。今ボランティアをしている人も何かテーマを決めて取り組んでほしい」と話した。
| 「ひとりひとりの死について詳細な記録を後世に残すこと」、「ひとりひとりがなぜ死ななければならなかったのかを解き明かすこと」「犠牲者が私たちに残したメッセージを読みとること」を目的として、98年7月から震災犠牲者全てを対象とした聞き語り調査を行っている。現在記録された「死」は約290人。主体となっているのは神戸大工学部及び都市安全研究センターの室崎研究室、塩崎研究室、北後研究室の学生で、毎年後輩へと引き継がれている。高田悟さん(院・1年)ら主要メンバー3人に話を聞いた。 |

打ち合わせをする調査会のメンバー
(神戸大工学部・室崎研究室で) |
●活動の内容
調査活動は遺族など協力者を探すことから始まるが、震災から6年以上が経過し、遺族の所在を知るのはきわめて難しいという。出版物で公表された資料や自治会などの口コミを頼りに、地域歩きによる地道な情報収集しかないのが現状だ。
協力者が見つかりアポイントがとれると、実際に調査員が訪問するヒアリングが行われる。語ってもらうのは当時の被災状況・心境、建物・間取り、生前のこと、震災の教訓などさまざま。ただし一方的に質問をなげかけるのではなく、犠牲となった人の死に至る過程を自由に話してもらう形をとっている。自由に話してもらうことで、人の死という事実を残したいという思いがあるからだ。彼らがやりたいのは「聞き取り」ではなく「聞き語り」なのだ。
ヒアリング調査の後、ヒアリング結果を文章にまとめ、確認ののち記録・資料は「阪神・淡路大震災記念協会」のもとに保存、管理される。現時点では研究資料として活用する場合以外は非公開となっているが、将来的には一般公開する方向で検討が進んでいるという。「他の人にもこれを見て何かを感じて欲しい」(高田さん)というように、次代への教訓、風化の阻止に活用してほしいという強い思いがある。
●調査を通して思うこと
メンバーは全員、震災を体験していない。彼らにとって震災は「違う世界のこと」、「防災研究の一環」でしかなかった。しかしこの調査で直に震災を感じて、想像以上の傷に衝撃をうけたという。3人は口をそろえる。「(自分たちの活動に)重みを感じる」と。
▽高田悟さん「私もそうだが震災を体験してない人はここまで大変なことになっていたことは知らないはず。犠牲者は数字でひとくくりにされることが多いが、実際にはひとりひとりに人生があった。そういう人たちを記録に残したい」
▽清水健太さん(院・1年)「遺族の話したくないことに踏み込むのだから抵抗もある。だけど悲しいで終わらせるのではなく次に役立てたい」
▽辻内源太郎さん(同)「悲惨な話を聞かせてもらえることは個人的にも貴重な体験。同じ惨劇を二度と起こしたくないと強く思った」
今年で終了 白いリボン運動
関学ヒューマンサービスセンター |
| 今年の1月17日で、震災7年目を迎える。この7年間、震災を伝え続けてきたヒューマンサービスセンターは阪神・淡路大震災メモリアル企画「白いリボン運動」を今年度で終了する。また1997年から西宮市内121か所の仮設住宅を撮影した写真7000枚の展示会も学内で行う。なぜ7年目という中途半端ともいえる今年に「白いリボン運動」を終了するのか。その真意を代表の山本有紀(社・3年)さんに聞いた。 |

笑顔で話す山本さん |
「変わっていかなければならない。もうそろそろ誰かがクギリをつけなければ。10年という大きな節目に向かってやるような延命的な処置は取りたくない。代表として最後のクギリをつける」と山本さん。震災の現状を鮮明に記憶している、おそらく最後の世代だ。
震災当時、山本さんは実家・静岡にいた。「全然意識しなかった」。震災は別世界のものだった。関学に入学した1999年。高校の頃からボランティア活動を行っていた山本さんは、大学でボランティア以外の活動を求めていた。しかし運命の歯車は、知らず知らずのうちに山本さんをボランティア団体・ヒューマンサービスセンターへと導いた。
秋、「仮設住宅調査プロジェクト」で初めて本格的に震災を‘体験’した。西宮市内に点々と存在する仮設住宅の様子を写真に収めた。調査を始めた1997年に生活感に溢れていた仮設住宅は、2000年、完全になくなった。後輩には仮設の存在すら知らないものも多い。復興が喜ばれる影で風化も進んだ。
そして、また年が一つ進んで2001年1月17日。自身2度目の「白いリボン運動」。白いリボン運動には4つの想いがこもっている。震災で亡くなった人々への「追悼」、ボランティアとして立ち上がってくれた人々への「感謝」、防災意識を忘れないでほしいという「再生」、7年間で培った様々な人・団体との「絆」。被災地である三宮・元町で白いリボンを配り、これら4つの想いを伝えた。さらに西は宮崎から東は東京まで、「知らない人に知ってほしい」と関係のあるNPO団体に白いリボンを贈ることで全国展開した。
「もう十分に伝わっているのではないか」。「震災」という事実を伝えることに2年間従事し、そう感じた。加えて「震災のことを知っている学生がいなくなる。今の1年生は当時小学6年生」。山本さんに、どうしようもない厳しい現状が迫った。そして「終わってしまうことは忘れてしまうことではない」と一つの結論を導き出した。その表情には様々な苦悩、葛藤のあとを感じることができる。震災当時から学生の活動を一被災者として支えてきた教授。「伝え続けてほしいという先生たちの気持ちはひしひしと伝わってきた」。
しかし、震災を原点として活動してきたヒューマンサービスセンターは震災だけの団体でなくなった。大学周辺の小学校、児童館などに出かけて、子供たちと遊ぶ、学童サークル「ひまわり」。学生に阪神間のボランティア団体を紹介する、ボランティア情報サービスネットワークの運営。ここ2、3年間で活動の幅は大きく広がった。
「変わっていかなければならない」。その一言には、複雑な思いと共に、代表としての強い決意がみなぎっていた。
ボランティアに防災知識を
セーフティリーダー学生ネット |
| セーフティリーダー(SL)学生ネット(http://www.saigai.or.jp/)は災害救援ボランティア推進委員会の「災害救援ボランティア講座」を受講し、認定を受けた学生の有志、OBで構成されている。防災・救命に関する基礎的な知識と技能を持った意識の高い学生の育成を目的に昨年4月に設立され、関東の主な大学のほか、愛知、三重、長野にネットワークが広がり、講習会、交流会などが行われている。(2001年12月現在、登録数は176名) |

東京総合防災訓練を受ける学生ネットのメンバー(提供写真) |
●活動の趣旨
活動の核である「災害救援ボランティア講座」は、ボランティア活動従事者が、防災や、救命・救急について最小限度の知識と経験を持つことの必要性から実施されている。そこには多くのボランティアがかけつけたものの、防災に関する知識や経験が全くなかったため、災害現場で十分生かされなかった神戸の教訓がある。
●神戸への想い
事務局の渡辺善明さんは「様々な分野に専門性を持つ学生が、身に付けた知識を忘れないよう自主訓練をしたり、交流できるこの場を大切に育んでいきたい」と学生ネットの運営に携わっている。
「震災当時、札幌に住んでいたので身近な事には感じませんでした。その後、大学生として関東に暮らすようになり、神戸の震災で多くの学生が犠牲になった事、その意味、知らなければならないことがあるのではないかと考えるようになりました。
震災によって浮き彫りになった避難所生活、仮設、復興住宅を通してコミュニティーの問題、ボランティア。神戸の経験を無駄にしてはならないと感じています。
私自身神戸から何を学び、今の自分に何が出来るのか考えました。だから、災害救援というよりも防災活動に関心を持ってきました。
神戸の学生といっても、肉親を失った人、被災体験のある人、ない人『もう過去の事やないか』、『忘れたい』等々、想いは様々です。私は9月に、震災復興ありがとうキャラバンの関係で神戸に行きました。イベントに参加して、三宮駅周辺を歩いて、『震災のことはとりあえずもうおしまい、ワールドカップに向けて取り組みましょう!!』という感じを受けました。 震災体験は着実に風化しています。
今、神戸の街はルミナリエで美しいのでしょう。震災から7年目を迎える神戸で、学生として今を暮らしている皆さんは次代に震災体験を語り継ぐ、メッセンジャーとしての大切な責務があると私は思います。
7年前、若い同世代の学生が、家の下敷きになって沢山亡くなった・・・今暮らしているこの地域で大地震が来て、同じことを繰り返したら神戸の学生の死は、一体なんだったのでしょう。
今だからこそ、真摯に受け止め、自ら学ぶ必要があります。神戸だからこそ出会い、向き合えることが山積みだと、そう思います」
人とのつながり大切に
茶屋明子さん(被災地NGО恊働センター) |
茶屋明子さん:神戸女子大学4回福祉学科専攻。
被災地NGО恊働センターとの出会いをきっかけに震災のボランティアに携わる。
1995年1月17日。ブラウン管越しの神戸の風景には実感が湧かなかった。
だが、当時中学校3年生だった茶屋さんの胸にはくすぶっている思いがあった。
震災のボランティアに関わりたい。彼女はそんな漠然とした気持ちを抱えながら
神戸女子大学に入学する。彼女は入学当初は「普通」の大学生だった。
しかし、大学2年のときに転機が訪れる。兵庫県主催の洋上セミナーで出会った
姫工大の草地賢一教授(故人)との出会いである。
彼女は、それを契機に、被災地NGО恊働センターの活動に関わるようになった。
行動力旺盛な彼女もさすがに、最初にNGОの門をくぐる時には勇気がいったと言う。
しかし、今や被災地NGО恊働センターの活動として、地域の人々とともに、タオルで象を作る「負けないぞう」活動や、「寺子屋セミナー」という震災をきっかけに話しあおうという集まりに参加している。また。学校でも、ホームレスの支援団体へ直接でかけたり、炊き出しに行ったりしている。彼女は震災を体験していない分、逆に何でも学ぼうという気概で活動に取り組んでいる。
しかし、彼女のやろうとしている意志が伝わらないもどかしさを感じるときもある。「『何がボランティアやねん。ボランティアやってって何の意味があんねん』
とか言われた時、恩着せがましいのかなと反省する時もあります」しかし「それも勉強のひとつです」と彼女は明るく笑った。
彼女は病院でソーシャルワーカーとして働いたり、福祉の知識を活かして海外のNGО活動に積極的に関わりたいと将来の夢を話す。
一方で、現実はまだまだ厳しい。行政側として住居の提供など、金銭的な支援や、
復興にひと段落着いたとの感が見られるが、現場を知る茶屋さんの目からすれば、
まだまだ援助が不十分だと感じる。
「自分が(NGОの活動に)関わり出した時には、すでに仮設住宅もなく、
見かけ上の震災の傷跡はなくなっていました。でも、三宮など華やかなイメージがある一方では、震災がきっかけで、ホームレスが増えたのは事実です。ホームレスの人たちの生の声を聞いて欲しいです」と語る。
「NGОの活動を通して、毎日新しい出会いがあります。助け合ったりすることってすごく大事なんだと思います。人とのつながりをもっと大事にしたいですね。学ぶ場所は大学だけじゃない。いろんなところに目を向け、一歩踏み出した学生生活をやって欲しいです」と最後に茶屋さんは熱っぽく語った。
|
住民の輪作りたい
加藤洋一さん(まち・コミュニケーション) |
「まち・コミュニケーション」スタッフ
加藤洋一さん(22)
明石高専専攻科建築都市システム専攻2年 |
 |
●ボランティアをするきっかけ
加藤さんは、震災当時中学校3年生で加古川に住んでいて、自宅周辺はあまり被害を受けず人ごとと思っていた。しかし「地震でつぶれない建物を造りたい」と建築を学ぶきっかけに。高1の時に「被災者だから助けてあげないと」と思い、家の近くにある仮設住宅でボランティアをした。
それから5年、専攻科1年の時の実習に「建築を学ぶうえで、現場の声も聞きたい」と「まち・コミュニケーション」を選んだ。実習は1カ月で終わるが、人間関係の重要さに気付かされ、その後も1年半活動を続けている。
●まち・コミュニケーションでの活動
都市計画や住宅政策の勉強をしながら、もちつきや慰霊祭など地域のイベントの手伝いや、被災地の情報を他の地域に発信するミニコミ誌「まち・コミ」の編集をしている。また他の地域に移り住んでいる人に御蔵に戻ってきたいかという調査をし、どういう街を造ったらよいか考え、専門家と住民のギャップを埋めようと努力している。加藤さんは「学校ではわからないことが学べるし、ここにいると楽しい」と話す。
●まちづくりに関して
「まち・コミュニケーション」の活動を通じ「建築を学ぶと言っても建物を造るだけではなく、住民の輪も重要である」と気付いた。「都市に住んでいると思っていても、自分が住んでいる『場所』がなければ生きられない」と都市住民の孤独を指摘する。少しでも住民の交流が深められるように、「まち・コミュニケーション」では、区画整理の時、土地を移動した人は仮設に入れるが、今は基準が厳しく空きが多い。そこで空いている仮設を、商売などに有効利用できるように神戸市にお願いしている。
●住民との触れ合い
「震災後焼けて骨とかが落ちてた御蔵がいやで引っ越した。でも戻ってきたら明るくなってた」と話をしてくれた人や、住民同士の触れ合いを通じて明るくなり、地震の体験を話せるようになった人を見て、「自分の活動が役に立っている」と実感し感動した。
自分自身があまり震災で被害を受けなかったので、どこまで話を聞いていいのか戸惑った。しかし、学生に対しても仲間に見てくれ、お酒を飲んだ時にむこうから震災の話をしてくれてうれしいと感じる。
●活動を通して思うこと
はじめは長田のことを何も知らなかったし、個人のレベルはどうなっているか知らなかった。自分の進むべき道を見つけることができて、人生の出発点になった。「まち・コミュニケーション」で「1番学ばせてもらったものは、住民の人との触れ合い」と笑顔で語った。
|
震災遺児を励ましたい
「頑張れ神戸っ子」 神戸大馬術部が主催 |
神戸大馬術部は子供たちが普段接することのない動物と触れ合うイベント「頑張れ!神戸っこ」を毎年11月に行っている。これは1998年、創部70周年記念行事の一環として、震災遺児を少しでも励まそうと、あしなが育英会と連携して実施したのが始まり。第1回目から深く関わってきた壇浦コ−チは「98年当時、震災で親を失った子供たちにはまだ震災のショックが強く残っていた。取材のためにカメラを向けられるのを嫌がる子もいたので、そうした繊細な子どもに不安を与えないよう気を使った」と当時の状況を振り返る。
昨年11月23日、第4回目となる「頑張れ!神戸っこ」が行われ、震災遺児とその関係者ら98人がつめかけた。乗馬体験に臨んだ子供たち。ヘルメットを身に着け、順番待ちしている間は、やや緊張している様子だったが、徐々になれ始めると、笑顔で周りにこたえていた。中には初めて間近にした大きな馬に泣き出す女の子もいたが、このイベントに何度も参加している「リピーター」も数多く来ていた。小学校5年生の大鳥居聡くんは「今回で4回目なので全然怖くなかった。おもしろかった」と心から楽しんだ様子だった。
馬場内の一角には、「エデン牧場」というミニ牧場が設けられ、子供たちは山羊、ウサギ、モルモットなど普段触れる機会の少ない動物と触れ合った。
午後からは一般公募の家族が参加。兄弟で来た坂本諒太くん(8歳)と苑香ちゃん(6歳)は「もし落ちたらと思うと怖かったけど、おもしろかった」(諒太くん)、「また乗ってみたい」(苑香ちゃん)と笑顔で話した。
最近、馬とのふれあいや乗馬体験を通して心身のリラックスをはかる「ホースセラピー」が徐々に認知されつつある。監督の新垣恒則さん自身、重度心身障害者に馬に親しんでもらう催しを開いた経験をもつ。「あしなが育英会には震災で親を失った多くの子供達がいる。震災で傷ついた子供たちが普段見ることすらできない動物とじかに触れ合うことで、少しでも楽しんでもらえれば」とこのイベントに込めた思いを話した。
「馬は人を癒してくれる力を持っているような気がします」と話してくれたのは、今回の行事を先頭に立って取りしきった主務の森下愛さん。「今日は多くの笑顔を見ることができて良かった。できれば、来年以降もこのイベントを続けていきたい」と充実感をにじませた。
|
特集 表紙ページに戻る。
|