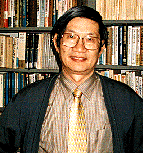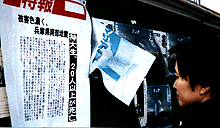1998年1月16日発行『神戸大学NEWS NET』紙面より

阪神大震災から三年
いま、後輩たちに伝えたいこと
 阪神大震災から三年。大学は大きな転機を迎える。震災を体験した四年生が卒業を迎え、大学生として被災した『世代』がいなくなるからだ。
阪神大震災から三年。大学は大きな転機を迎える。震災を体験した四年生が卒業を迎え、大学生として被災した『世代』がいなくなるからだ。
突き上げるような激震を体で感じ、がれきの町を友を探してさまよい、水を汲み、避難所で暮らし、ボランティアに打ち込んだ『世代』のほとんどが、この神戸大学から巣立っていく。
震災直後の日々から、先輩たちは何を学んだのか。卒業を前にした四年生や、大学院生、OB、教官に、「いま、後輩たちに伝えたいこと」を聞く。(『神戸大ニュースネット』『関学新月トリビューン』『神女院大K.C.Press』の三紙の共同企画です。)
【写真】ヘリ中継の画面には、下宿街が広がる灘区六甲町あたりが映し出された。
8時50分。すでに猛火に包まれている。(95年1月17日 NHKテレビより)
ご意見、ご感想をお寄せください。
unnnews@tky.3web.ne.jp
■関連特集記事:
炎上する西尾荘。友を助けられなかった……
「あの日をずっと覚えていて欲しい」
井口克己さん(朝日新聞社勤務/当時=営・三年 映画研究部Rick's)
 【写真】ヘリ中継の画面には、燃える灘区六甲町あたりが映し出された。炎の見えるあたりが、西尾荘付近。時報の下が、JR六甲道駅。(1995年1月17日 ニュースネット撮影)
【写真】ヘリ中継の画面には、燃える灘区六甲町あたりが映し出された。炎の見えるあたりが、西尾荘付近。時報の下が、JR六甲道駅。(1995年1月17日 ニュースネット撮影)
 【写真】中村公治さんら、三人の神戸大生が亡くなった、神戸市灘区六甲町2丁目の西尾荘跡。(1995年3月18日 ニュースネット撮影)
【写真】中村公治さんら、三人の神戸大生が亡くなった、神戸市灘区六甲町2丁目の西尾荘跡。(1995年3月18日 ニュースネット撮影)
 【写真】現在の西尾荘跡。神戸市が土地を買い取り、震災が一年とたたないうちに、新しいアパートが建った。(1998年1月3日 栃谷亜紀子・撮影)
【写真】現在の西尾荘跡。神戸市が土地を買い取り、震災が一年とたたないうちに、新しいアパートが建った。(1998年1月3日 栃谷亜紀子・撮影)
|
炎につつまれていく西尾荘は、一生忘れられない光景だろう。
当時・経営学部三年生だった井口克己さん(24=現・朝日新聞東京本社厚生部勤務)は、親友の中村公治さん(当時・経営・三年)を亡くした。
二人は同じ映画研究部Rick'sに所属していて、同じ名古屋の高校出身。「僕は(灘区)烏帽子町で、中村は六甲町にある西尾荘に住んでいてお互い近かったこともあり、すぐ親しくなりました」という。
震災前日の十六日、井口さんはJR六甲道駅で中村さんを見かけた。バイトに行くために駅にいたんだろうと井口さんは言う。「このときは、また夜に下宿に行けばいいかと思い声をかけることはしなかったんです」。その日の夜、井口さんは電話をしたが、中村さんは飲みに行っていて、この日は会えなかったという。
そして、あの日。「大きく揺れました。揺れが収まったので外にでると、家の向かいの木造の家の一階はほぼ全滅で、近くの烏帽子中学は火事でした。とりあえず暗かったので明るくなるまで待って、午前七時ごろ名古屋の実家に電話で元気だと伝えました」。
スキー板がのしかかり、どうしても助け出せない
午前八時ごろ。中村さんの下宿、西尾荘に行った。「もうどこかに逃げ出したと思っていたんですが、大家さんが『中村君はまだ中にいる』と言ったのであわてて向かいました。そこで見たのは、手だけが出ている中村の姿でした。体の上にはコンクリの床、頭にはスキーに行くからと言って、貸したぼくのスキー板がのしかかり全く動かない。僕らはがむしゃらに中村の上にあるものをどけにかかったが、いっこうにらちがあかない。そこに年輩のおじさんがシャベルを持って現れ、手際よく作業を進めたんです。この時僕は、『よかった中村を助けられる』とよろこびました」。
ノコギリを使って梁などを切りのぞき、ほぼなくなろうとしているとき、外から『火のまわりが速い、早く出てこい』と言う声がした。「確かに火は迫っているがもう引っぱり出せると思いました。でも、僕のスキー板が邪魔して動かないんです。もう間に合わないと思いました。僕はもっとも敬愛すべき友、中村を助けられませんでした」。
焼け跡を掘った。骨だけになったなきがらがみつかった
外に出た井口さんたちが振り返ると、西尾荘は炎と轟音とともに二階部分が崩れ落ちていった。「目の前で見殺しにしてしまった。こんなに悔しいことは今までではじめてでした。信じられなかった。『何で消防ははやくこないんだ』『神様はいないのか』『何でよりによって一番死なせてはいけない人がこんなところで死ななければならないのか』と思いました。でも、もう中村は、帰ってこないんです」。
翌十八日、名古屋から駆けつけた中村さんのお父さんらと、西尾荘の焼け跡を掘った。ほとんど骨だけになった、中村さんのなきがらがみつかった。
「今となってはもっとうまく(救出を)できたのではないかと思う。なんだか悲しいというより悔しかった」。あれから毎日、西尾荘に行き、理由もなくただ立ちすくんでいたという。 「(震災を)経験していない人にとっては分からないと思う。それはしょうがない。でも、そういうことがあったということは覚えていて欲しい。これからもずっと一月十七日は来るけど、何年も経ったからといって『今更』とは言って欲しくはない」と語る。
社会人になってから二年。井口さんは、その後も半年に一回は神戸を訪れる。今度の一月十七日も神戸に行く予定だという。
|
安否確認に追われた日々
「語り継ぐことを大切に」
神木哲男さん(副学長/当時=経済学部長)

【写真】地震直後の国際文化学部図書室の開架閲覧室。
(1995年1月17日 附属図書館・撮影)
|
神木哲男副学長は、震災当時は経済学部長として、教職員や学生の安否の確認や、授業の再開に奔走した。
灘区長峰台にある神木さんの自宅は半壊した。「下の方から煙が見えた」という神木さんは、一月十七日、歩いて大学へ向かった。八時には到着していたという。「大学では地震対策は何もしていなかったからね。とにかく一日目は正確に覚えていないほど夢中でした」と当時の状況を語った。
教職員と学生の安否確認を急いだ。学生一人一人の下宿に電話をし、いなければ実家に電話をするという作業を行った。「学生が亡くなったという情報がだんだん入ってきて本当につらかった。全員の安否が分かったのは十日以上後になりました」と当時の苦労を語る。
一月二十日が経済学部の卒論の締め切りだった。「通常は締め切りは厳密なのですが、使用していたフロッピーがだめになってしまった人などがいたので、締め切りを延ばすという特別措置を取りました」と苦笑いする。
「特に印象に残っているのは、学生間で温度差があったことです」と神木さんは強調する。「神戸の学生がボランティアなどに走り回る一方で、少し離れた所では家でのんびりテレビを見ていた学生がいたことも事実です。テストがレポートに変わって喜んだ人もいたでしょうね」と言う。その温度差を少しでもなくすため、四月から経済学部では震災講座を開設。神戸新聞社などから講師を招き、学生の認識を深めた。
「『今日は復興に近づけただろうか』と思いながら眠る毎日でした」という神木さん。
「震災で大きな痛手を受けたが、学生の中からボランティアが生まれ、いろんな人に助けてもらった。三年間で様々なことを乗り越え、神戸大としても新しいスタートを切ることができたんじゃないでしょうか。これからは、全国の若い人に語り継いでいくことが大事でしょう」。
九十八年一月十七日は、センター試験当日でもあり、普段は一般の人は学内に入ることはできないが、神戸大の慰霊碑に来た人は入れるように特別な措置をとっている。
|
「俺が死んだら団旗になる」
応援団長の言葉を胸に
中村治人さん(農・四年/当時=同・一年 応援団)

 【写真上】高見団長が亡くなった、灘区友田町の盛華園アパート。2階の自室で見つかった。
【写真上】高見団長が亡くなった、灘区友田町の盛華園アパート。2階の自室で見つかった。
(1995年3月21日 ニュースネット撮影)
【写真下】現在の盛華園アパート。震災からほぼ二年たった、96年暮れに完成した。今も神戸大生らが入居する。
(1998年1月3日 栃谷亜紀子・撮影)

 【写真上】震災から二年。震災の日に、中村さんは六甲台の慰霊碑を訪れた。
【写真上】震災から二年。震災の日に、中村さんは六甲台の慰霊碑を訪れた。
(1997年1月17日 堀江悟・撮影)
【写真下】中村治人さんは、橙色の団旗を見ると高見さんを思い出すという
(1997年12月 副野吉史・撮影)
|
震災で亡くなった神戸大生三十九人の一人に、応援団団長だった高見秀樹さん(当時済・三年)がいる。 震災直後の混乱の中、応援団の連絡先になったのは、当時農学部一年生だった中村治人さんの下宿。昼には電気がつき、現役部員もOBも集まった。これだけのメンバーが集まることはめったになかった。「でも高見さんだけ連絡がない」。
高見さんの下宿先だった灘区友田町の盛華園アパートの大家さんに聞いても、全員外に出たという。病院にいるのではと近くの病院を探し回ったが、それらしい人もいない。翌日もしかしたらと、がれきになったアパートの中を探してみると、高見さんは変わり果てた姿で発見された。
「俺が死んだら団旗になる」高見さんがそう言ってたのを覚えている。当時、三年生の団長は近寄りがたい遠い存在だった。「応援団への思いが強かったんだろうな。俺には言えない」。去年副団長を務めた中村さんは橙色の団旗を見ると高見さんを思い出す。 震災の翌年の三月には、六甲台に慰霊碑が建立された。しかし今ではその存在すら知らない学生が増えている。「去年なら直接体験した人も半分いたが、今は俺らだけだし、もう卒業やしな…」。追悼の気持ちや今後どうしていったらいいかを考えることはあるが、年々、被災経験のない学生が増え、自身も気持ちの変化は止められない。
「経験してないからしゃあないって感じかな」。
今春、中村さんは洋酒会社に就職する。
|
ゼミ生を失った悲しみ
「一日一日を大切にしたい」
五百旗頭 眞さん(法学部教授)

【写真】震災直後。倒壊した阪神高速。現代日本の建造物はあまりにもろかった。
(1995年1月17日午前9時30分ごろ。神戸市東灘区深江で。 ニュースネット撮影)
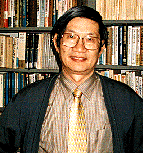
【写真】「今何か持っているものは出しきるべき」と話す五百旗頭教授
(1997年12月 副野吉史・撮影)
|
「彼は格別に真剣に私に向かってきましたね。彼には(当時)ガールフレンドがいたんですが、ゼミで僕が彼を評価したら、それこそ天にも上る気持ちでその彼女に報告したって言ってましたよ(笑)」。
法学部の五百旗頭眞教授(いおきべ・まこと、日本政治史専攻)は大切なゼミ生を震災で亡くした。卒業論文で大論文を書くと意気込んでいた最中に召天した森渉さん(当時法・四年)。クリスチャンだった彼のひたむきな姿を、教授は鮮明に心に抱いている。また森さんのことを批評したら、「もう一度そのことについて彼女と議論しあって、僕にぶつかってきたんですね。がんばっていましたよ」。ゼミ内での議論の中でも、森さんは常に自分の意見を強く主張していた。それが多数派であろうとたった一人であろうと。
軽音楽部に所属していた森さんは前の晩に友人の家で飲んでいたが、泊まらず下宿先に帰り、北側にあるベッドで寝ていた。南側にこたつがあり、そこで彼は勉強していたが、卒論と最後の試験に備え、風邪をひいてはいけないと大事をとったのだという。しかし皮肉にもそのベッドの方へ梁は直撃した。
ジャーナリストを目指し新聞社に内定が決まっていた彼にすすめた本は、二十世紀最高のジャーナリストと呼ばれるウォルター・リップマンの評伝。「森くんはリップマンにそれ以降心ひかれていたようですね。年下のゼミ生にも彼の本をすすめていました」。
毎年ゼミで発行する小冊子「真実の道」は、九五年の春の号は森さんの追悼号となった。そこには『森さんへ』と題して、教授や当時の三、四年生による手記が綴られている。ある後輩はその中で彼に対してこう振り返っている。「まず外見からいえば、いつも少し太めのストレートパンツに、布の肩さげかばん。全体的に少しだぶっとした服が、お好きなようだった。語り口は、独特で、人なつこくゆっくりとしていて、いつも関西弁」。彼の人間味がよくわかる。
五百旗頭教授は自身を楽天家と呼んでいるが、そんな彼もあの日以来、一日一日を大切にしたいという気持ちが芽生えた。「将来のために力を温存しておこうとしても、そんなの保証できないですね。今何か持っているものは出すべきですよ。人生の中で決勝戦って、ないかも知れん。学生も、そして私もそれを肝に銘じて生きていきたい」。
|
デマ、パニック、恋人の死
「一人一人に、つらいことがあった」
吉田愛子さん(仮名 発達・四年/当時=発達・一年)
|
|
大きな揺れで、吉田愛子さんのテレビは落ちた。たまたまその日はテレビの近くで寝ていなかった。「もし、いつも通りの場所で寝ていたら、おそらく死んでいたと思う」と神戸市灘区篠原中町に住んでいる吉田愛子さん(当時=発達・一年)は語る。
アパートを飛び出した吉田さんは阪急を境に南がめちゃくちゃにつぶれていたのを覚えている。「すぐに公衆電話で実家に無事を伝えようとしたが、すごい列ができていました」。余震が怖くて家に入ることもできずに、しばらく近所の人と避難していたという。「ガス警報機の音がうるさかったのが印象的です。あちこちでガスの臭いがして警報機が鳴り止まなかった。今でもあの音はいやです」と。
友人の安否確認のため、街を歩き回った。ある家の前を通りかかったとき、若い男性に声をかけられた。「石を運ぶのを手伝ってもらえませんか」。なぜか、その男性は、石を抱えて、その家の庭にいた。その男性はフィアンセを亡くしたという。「すみません、時間がないのです」と言うと、その男性は「石を運ぶくらいいいじゃないか」と、急に怒り出して、その石を投げてきたという。みんなが、極限状態にあった。パニックを起こしていた。人間が信じられなくなって、怖かった。
山手の友達の家に避難していたが、十七日の夜には西宮北口駅まで歩いて行こうということになったという。「デマが流れたんですよ。三宮から火が押し寄せてくるから西には行くなって。それで、六時間かかって西北まで行ったんです。行く途中も倒れかかっているマンションの下を通るときとか、生きている気がしなかった」。
そして、一月三十日は神戸大の登校日だった。「友達の彼氏が亡くなったことを知りました。友達は、さすがにはじめなかなか立ち直れなかった」。でも、今は命日には彼氏の実家に行っているという。
「一人一人に、つらいことがあった。そのことだけは後輩たちに分かっていてほしい」と語る。
|
「加藤が死んだ」
どうしようもできない無力感
河野道紀さん(法・四年/当時=法・二年)
|
|
「加藤が死んだ」という電話を友人から受けたのは十九日だった。河野道紀さん(現、法・四年)は、ISAでいっしょに活動していた加藤貴光さん(当時・法・二年)を亡くした。西宮市のマンションが倒壊して、下敷きになって亡くなった。河野さんは加藤さんの広島の実家に駆けつけ、葬儀に参列した。
震災当日、河野さんは篠原台の下宿で寝ていた。突然の激しい揺れに目を覚ましたが、再び眠ってしまったそうだ。「本棚が倒れたりしたんですが、篠原台では被害の大きい灘区にあって被害者がゼロでした」という。「すごい地震が来たな」と実感したのは阪急六甲、JR六甲道に降りてからだという。
加藤さんをISAに誘ったのは、実は河野さんだった。「僕らは学番が近く、同じゼミだったんです」という。「彼は一回生のときESSに入っていたんですが、僕がISAに誘いました。海外の大学生との交流など、一緒に活動していました」という。
十七日のうちに、ISAの友人から「加藤と連絡が取れない」という電話が入った。しかし当時の状況から「電話回線が切れたせいだろう」と思ったという。友人から、悲報を伝える二本目の電話が入ったのは二日後だった。
「実感が湧きません」と河野さんは振り返る。「地震とか自然災害はどうしようもできない。……人に何を伝えたらいいのか分からない」という。「ただ若いときにもこういうこと(友人を亡くすこと)があるんだなと思った」。突然の惨事で友人を亡くして三年。いまでも、うまく表現する言葉が見つからない。
|
被災地の痛みに心寄せて
「次に生かせるものはないか」
稲村和美さん(法学研究科・二年/当時=法・三年 総合ボランティアセンター)

【写真】国際文化学部の南にある、一王山仮設住宅。38世帯のうち半数は空室になっている。入居者が公営住宅などに移ったためだ。向こうにみえるのは工学部。
(1998年1月3日。神戸市灘区一王山町で。 ニュースネット撮影)
|
震災救援隊とともに学生の震災ボランティアの中心となってきた総合ボランティアセンター。今も、被災住民へのボランティアはもちろん、高齢者介護やあしなが遺児への支援活動も一層積極的に行っている。しかし「活動的にそろそろ総括・検証といった時期」と元代表の稲村和美さん(院・二年・法学研究科・法社会学専攻)。
「三年で(震災での)特例措置が切れるケースが多い。見えないところで今後一層しんどくなる人も出るやろうし、今まで先送りされてきた問題がさらに追い打ちをかけてくるやろうね」。ボランティアを通して、被災住民の気持ちが痛いほど身にしみている稲村さんだけに、思いは複雑。「被災した人たちにもいろんなニーズがあって、それをいかに私たちの問題としてとらえるかがボランティアを考える意義。ボランティアのやりすぎがかえって自立を阻害するというが、自立できない人にはそれなりの事由があるはず。そうした阻害要因を取り除く活動が必要なのに…」。
震災を機に総合ボランティアセンターに入った稲村さんは当時法学部三年生。「あれ以来学ぶことは数知れず。あの日がなければ院にも行かなかった」。「犠牲になった人のためではないが、次に生かすものを形にして(私たちが)引き出せなければ、これだけの体験をさせてもらって彼らにあわせる顔がない」。
ボランティアを続けて来た稲村さん。そんな彼女を慕いながら、後輩もマイペースに自分なりの考えで活動している。
しかし、次第に震災の色が薄れていることは稲村さんも認めざるを得ない。「今、当時を体験してない学生に無理に関心を持てというのは不可能。でもせっかく四年間でも神戸にいるのだから、被災地の情報には関心は持ってほしい」。
|
「救出できなかった悔しさバネ」
講義とボランティア両立の日々
星野裕志さん(経営学部助教授)
|
|
神戸大の星野裕志助教授(当時助教授、国際物流、国際経営環境専攻)は、自宅のある神戸市東灘区住吉東町で震災に遭い、以来ずっとボランティア活動を続けている。「東灘区では震災で九十三%の家屋が倒壊して、とにかくみんなが傷ついていた。つまり他人事じゃない、自分もそうなっている可能性だってあったわけだから。だからボランティアとか、そういうことじゃない」星野助教授はこう振り返る。
震災から三年が経とうとする今も活動を続ける動機は一体何なのか。「…顔を土だらけにした女の子が何かにむかって必死に叫んでいる。行ってみると、三階建てだったはずの看護婦さんの寮が一階くらいの高さにつぶれてて…。三十分くらい、一緒になって呼びかけたり掘り起こしたりしてたんだけど、その時は結局あきらめてその場を立ち去った。次にそこを通りかかって見ると花が供えてあって、ああ亡くなったんだなって。でも震災後何日も経ってから発見されて、それでも生きていた人がたくさんいたっていうことを知ると、どうしてあの時簡単にあきらめてしまったのか、あの時の自分には助けてあげることができたかもしれないのに、そう思うと悔しくて仕方ない…。この後悔や無念さが、活動を続けている動機なのかもしれない。きっと一生持ち続けるものなんだろうけど」。
震災を経て、「あれから確実に何かが変わった。一期一会じゃないけど、今まで以上に、機会や出会いを大切に思うようになったことかな…。助けてあげられる機会はあったのにできなかった、あの後悔や無念さは忘れられない」。何か伝えたいメッセージがあるとしたら、多分そういうことになると思うと、星野助教授は静かにそう語った。
|
全国から来た救援
地元との「ギャップ」なぜ
馬場孝輔さん(農・四年/当時=農・一年)
|
|
馬場孝輔さんは、震災当時大学一年生だった。西宮市門戸荘の自宅で被災。「かなりの揺れで体が壁から壁に飛ばされました。起きてすぐマッチを付けようとしたんですが、(手が震えて)つけられなかったんです。そこで初めて自分がこわがっているということが分かりました」と。「一時間程かかりマンションから出ると、外付けの非常階段は倒れ、新幹線の陸橋が落ちたり、辺りでは煙りがあがっていてすさまじい状況でした」。マンションを出て、返事がない家を助けたり、親は食料と住む所の確保など、一日目は時間が過ぎるのが早かったという。
「三日目からようやく友人のおばあさんの家へ移ることができたんです。それからずっとボランティア活動の日々でした。ボランティアも各地から来てくれてました」。しかし、理想のボランティア像をもって来た人と、地元の被災者との間での行き違いが多かったという。一日中何かをしていなければいけないということもなく、特にすることがなかった日もあるという。だが、外から来た人にとっては常に何かをしていなければいけないと思っていたという。「そこでギャップを感じたんです。地元の人に対して怒る人もいました」。
地震の二日前の成人式で再会した同級生が、テレビの死亡者欄の名前にでていた。知人が五人亡くなった。「死ぬときは死ぬ、これだけは震災で分かりました」と語る馬場さん。この春からは農学部の大学院に進学する予定だ。
|
遺体を掘り起こしてくれたのは
となりのクリーニング屋さんだった
庄子猛さん(済・五年/当時=済・二年)
|
|
「二階が落ちて一階になっていました。ほんと全壊というかんじで。なんか変わり過ぎていて事態がのみこめなかった。下宿に何度か行ったこともあり、知っていた分なおさらそうでした。彼の遺体はもうその時見つかっていたんですけど」。
当時、神戸大生協LANSの食堂でアルバイトをしていた庄子猛さん(済・五年)さんは、バイト仲間の林宏典さん(当時済・二年)を亡くした。灘区将軍通の安田文化住宅の一階で、圧死だった。
「一月十七日はとりあえずLANSへ行きました。みんなの安否を確認したかったこともあるし、何より僕の家が倒壊してしまっていたから」。午後二時ごろのLANSには千人くらいの人が避難していたという。「でも区役所から届けられたのはリンゴがたったの百個だけ。それで僕たちが何かしなければ、ということになって炊き出しをしていました。そこから『救援隊』が生まれたんでしょうね」。しばらくたって、林さんの下宿の辺りから煙が立っているのが見え、あわてて駆けつけた。
庄子さんは今でも月に一度手を合わせに、林さんの下宿のあった場所に行く。
林さんの遺体を掘り出したのは、隣のクリーニング屋さんだった。区役所から届いたのは、たった百個のリンゴだった。「行政が行う救援活動はあてにならない。頼りになったのは、地域のつながりや友人関係。そうした関係を大切にしなくては、いざと言うときに困ると思う」。
|
震災を機にイベント
原点は学生と地域の交流
松本邦裕さん(経済卒/当時=大市大 院・二年 神戸大学学生救援隊)

【写真】昨年、三回目の「灘チャレンジ」が行われた。会場の都賀川公園には約5000人の市民が集まった。
(1997年6月1日。 堀江 悟・撮影)
|
総合ボランティアセンターとともに学生の震災復興ボランティアの旗手となった『神戸大学学生救援隊』。震災を機に企画されたイベント『灘チャレンジ』は今でも毎年六月に行われ、学生と地域住民との交流の場として毎年恒例の行事となっている。
「何かをしようと一生懸命になってるのはごく少数。神戸にいつまでも金を送ることがいいことではない。アカデミックな人なら今後どうすればいいかを真剣に考えるべきだ」と救援隊名誉事務局長補佐の松本邦裕さん(当時院・二年)は語る。
|
倒壊、避難、炎上
ありのままの写真をホームページに
乾秀之さん(自然科学研究科・博士二年/当時=同・修士一年)

【写真】震災当日の写真。灘区篠原南町の乾さんの下宿前の住宅は、倒壊してしまった。
(1995年1月17日。乾秀之さん撮影)
|
「しばらく揺れが続き収まってから辺りを見渡しました。妙に静かできれいな月が出ていたのを覚えています」。震災当時、自然科学研究科修士課程一年で遺伝子工学を研究していた乾秀之さん(現・博士課程二年)は灘区篠原南町の木造二階建てのアパートに住んでいた。
「六甲小学校に向かう途中にも歩いていられない程の揺れが何度となく襲い、あちこちでガスの臭いがして緊張の連続でした。」。その日は大学の会議室に泊まった。「震災でやさしくなったんじゃないでしょうか。運命はわからない。でも、どうやって生き残るかとか、困った時の対処などは学びました」。
街の中を歩きながら夢中できったシャッター。乾さんは、個人のホームページに、その写真と体験を記録している。倒壊したアパート、煙におおわれる街、迫る炎。サイバー上に乾さんの記録は刻まれている。
乾さんのホームページはhttp://133.30.114.124/doc./inui.html。
|
44人の追悼手記を紙面に
「神大に記憶とどめておきたい」
里田明美さん(中国新聞社勤務/当時=自然科学研究科修士一年 ニュースネット委員会)
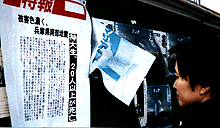
【写真】学内に貼り出された本紙特報。安否確認がまだまとまらず、「神戸大生20人以上が亡くなる」という見出しになっている。この特報が共同通信に転載され、全国の地方紙やスポーツ紙に掲載された。
(1995年1月27日。ニュースネット撮影)
|
「直感で震度六はあるなと思いました。外に出ると、ケガをしている人もいる、電柱は倒れているで大変でした」。自然科学研究科修士一年だった里田明美さんは、午前八時すぎ灘区高羽町の下宿から大学の研究室に着いた。
当時、放送委員会の学外にニュースを送る報道部門(後にニュースネット委員会に改組)のキャップでもあった里田さん(現・中国新聞整理部勤務)はすぐ、取材を始めた。
倒壊した下宿に閉じ込められた友人の談話。緊急に食料品の販売を始めた生協。安否確認に追われる各学部……。次々に記事を送信した、『神大生二十人以上死亡』の貼り出し特報は、共同通信がほぼそのまま転電し、全国の新聞に載った。「同じ神大生がたくさん亡くなった。どんな人だったのか、覚えておいてほしかった」そんな思いがずっとあった。震災から一年たって、亡くなった学生や教職員四十四人の追悼手記をまとめた。家族への電話取材は辛かった。「なんて声をかけたらよいか。聞くことによって傷を深めるんじゃないだろうかという葛藤もありました」。何が運命を分けたのか。いつもと違うことをして亡くなった人と、違うことをして助かった人。特集号を発行後、遺族からお礼の手紙をもらい、少しほっとした。
「人間は忘れる動物だと思う。忘れないために残したかった」。故郷・広島の新聞社で働く今も、亡くなった学生のお母さんとの文通が続いている。
|
震災を伝える約三万タイトルの資料
六甲台の『震災文庫』
稲葉洋子さん(神戸大付属図書館 情報管理課情報管理第一掛長)

【写真】震災文庫には、書籍だけでなく、告知ビラや大学新聞なども収集されている。(附属図書館提供)。
|
物言わぬ、チラシ、ビラなどの資料たちも、私たちに当時の状況を語りかけてくれる。現在、六甲台にある図書館の震災文庫には、約一万三千タイトルもの資料があり、細かく分類するとその数は約三万タイトルになる。震災文庫を管理しているのは、神戸大付属図書館の情報管理課情報管理第一掛長の稲葉洋子さん。
震災文庫の資料は、購入したり、寄贈されたりさまざま。資料もボランティアの行動記録、記者発表資料、神戸商工会議所求人情報、都市計画学会からの被災状況の分布図、ここで風呂が入れるなどのチラシと震災に関するもののすべてを集めた。中には一部しかないものまで寄贈してもっらたり、図書館に保存してもらう方が安心だからと貴重な資料の提供を受けたりした。
稲葉さんは震災文庫について「資料を見ていると当時の状況がひしひしと伝わって来ます。神戸大の歴史の一つだと思います」と語ってくれた。
「震災文庫」のホームページはhttp://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/。
|
■関連特集記事:
 【写真】ヘリ中継の画面には、燃える灘区六甲町あたりが映し出された。炎の見えるあたりが、西尾荘付近。時報の下が、JR六甲道駅。(1995年1月17日 ニュースネット撮影)
【写真】ヘリ中継の画面には、燃える灘区六甲町あたりが映し出された。炎の見えるあたりが、西尾荘付近。時報の下が、JR六甲道駅。(1995年1月17日 ニュースネット撮影) 【写真】中村公治さんら、三人の神戸大生が亡くなった、神戸市灘区六甲町2丁目の西尾荘跡。(1995年3月18日 ニュースネット撮影)
【写真】中村公治さんら、三人の神戸大生が亡くなった、神戸市灘区六甲町2丁目の西尾荘跡。(1995年3月18日 ニュースネット撮影) 【写真】現在の西尾荘跡。神戸市が土地を買い取り、震災が一年とたたないうちに、新しいアパートが建った。(1998年1月3日 栃谷亜紀子・撮影)
【写真】現在の西尾荘跡。神戸市が土地を買い取り、震災が一年とたたないうちに、新しいアパートが建った。(1998年1月3日 栃谷亜紀子・撮影)

 阪神大震災から三年。大学は大きな転機を迎える。震災を体験した四年生が卒業を迎え、大学生として被災した『世代』がいなくなるからだ。
阪神大震災から三年。大学は大きな転機を迎える。震災を体験した四年生が卒業を迎え、大学生として被災した『世代』がいなくなるからだ。

 【写真上】高見団長が亡くなった、灘区友田町の盛華園アパート。2階の自室で見つかった。
【写真上】高見団長が亡くなった、灘区友田町の盛華園アパート。2階の自室で見つかった。
 【写真上】震災から二年。震災の日に、中村さんは六甲台の慰霊碑を訪れた。
【写真上】震災から二年。震災の日に、中村さんは六甲台の慰霊碑を訪れた。