いよいよ1980年に「六甲祭」がスタートしました。黎明期の六甲祭の動きを、神戸大学大学文書史料室所蔵の各学部の「卒業アルバム」や『神戸大学新聞』、放送委員会の『KUBC PRESS』(1981年創刊)、ニュースネット委員会の『神戸大学NEW S NET』(1995年創刊)などの学内メディアの記事などで探ります。<編集部>
-1-1024x500.png)
(画像:初期の六甲祭のポスターやパンフレット表紙)
神戸大の学園祭の歴史を探る連載。今回からは、1980年から始まり、現在も開催されている、六甲祭の変遷をたどります。
六甲祭は、全学部統一祭を目指して始まりましたが、名実共に全学祭として定着するまでには時間を要したようです。
1983年11月6日付の学内紙『KUBC PRESS』(神戸大学放送委員会発行)には、第3回六甲祭実行委員長の細見伸広さん(当時理・3年)が、「六甲祭も3年目になったけど、まだ六甲台祭のイメージが強い。六甲台は伝統があるから実行委員が出てくるけど、毎年実行委員の所属学部が片寄って困る。文・工は自治会がないし」と取材に答えています。
この年は、それまで模擬店やアマチュアコンサートが行われていたハイツキャンパス(現・六甲台第2キャンパス)が自然科学研究科棟の建設工事で使用できないため、「教養部(現・鶴甲第1キャンパス)、学生会館にも模擬店・コンサート・全体企画が置かれ、今までより会場が広くなった」と記事にあります。
使用するキャンパスも何度か変更になり、2013年にはやはり建設工事の影響で六甲台地区での開催ができず深江キャンパスで行われました。
1995年の阪神・淡路大震災、2020年からの新型コロナウイルス禍もなんとか乗り越えて、45年を経た今年(2025年)も、無事行われました。
○ ○
「六甲祭」の歴史をたどるために、まずポスターやパンフレットなどの資料をあたろうと、六甲祭実行委員会のボックスを取材で訪れることにしました。
六甲祭をはさんで、2024年10月下旬と、開催直後の12月上旬の2回訪問しました。ボックス内には、歴代のポスターや、ゲストのサイン色紙などがずらり並んでいて、許可を得て写真に収めさせてもらいました。
2回目の訪問では、元六甲祭実行委員会のメンバー(2009〜2011年)だった松本充弘さん(現・人文学研究科特命助教)にも同行してもらい、松本さんが2011年に仲間とボックスの資料をまとめた際に見つけたパンフレットを綴じたファイルなどを見せてもらおうと期待が高まったのですが、残念なことにその行方が現在わからなくなっていて、今回はまとまったパンフ資料にはたどり着けませんでした。
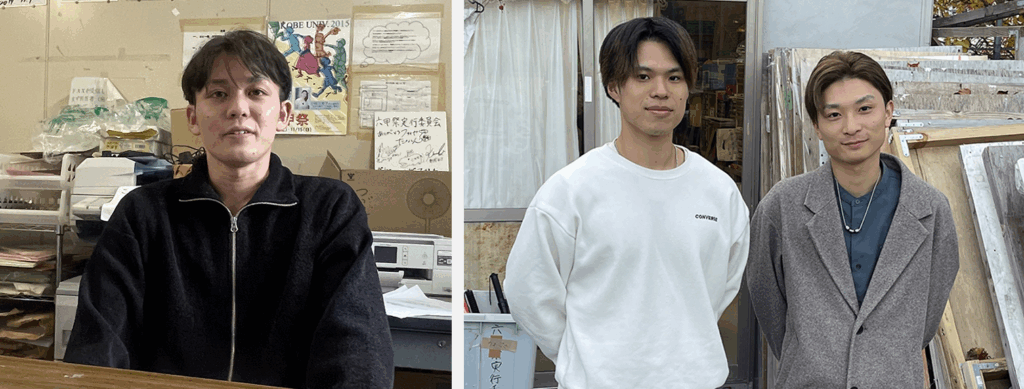
(写真:取材に協力いただいた、2024年度六甲祭実行委員会 対外副委員長の岡本一真さん(左)=2024年10月28日撮影=、2024年度六甲祭実行委員会 委員長の津島風斗さん、2025年度六甲祭実行委員会 委員長の越峠遼大さん=同12月6日撮影=)
そこで、今回の連載では、卒業アルバムと、1982年創刊の放送委員会の『KUBC PRESS』、1995年創刊のニュースネット委員会発行『NEW S NET』、そして松本さんの記録、それに初期の実行委員メンバーの資料をもとに、六甲祭のテーマや主な出演者の記録を再現することにします。
(◯印の項目は1982年創刊の放送委員会『KUBC PRESS』から、※印は六甲祭実行委員OB松本充弘さんの記録から、□は同・圓山茂夫さんの資料、□□は同・宮地基さんの資料、□□□は同・寺島巨史さんの資料、□□□□は同・吉田博子さんの資料から構成しました。)
.jpg)
(画像:1980年 第1回六甲祭のパンフレット □)
1980年 第1回 ※
テーマ「Come Together―創り出せ我らの文化を 築け熱き力で」
後夜祭 もんた&ブラザーズ(生協企画)
▽ポスター画像は、1982年の卒業アルバムから。医学部の大倉山祭の日程sと一緒にレイアウトされている。
▽第1回六甲祭実行委員会の企画運営局・宮地基さん(当時法学研究科)がまとめた、1985年の実行委内部資料「六甲祭資料Vol.2」によると、参加団体は教育学部、理学部、農学部、法学部、経済学部、経営学部、教養部、住吉寮、国維寮、女子寮となっている。
▽11月14日、生協企画の「後夜祭」として、もんた&ブラザーズのコンサートが六甲台講堂で開催された。□□□□
.jpg)
(画像:1981年 第2回六甲祭のパンフレット □□□)
1981年 第2回 □
テーマ「Come Together―明日へのステップ」
プロコンサート スターダスト レビュー
▽前述の内部資料によると、新たに文学部が参加、工学部から有志が参加。
.jpg)
(画像:1982年 第3回六甲祭のパンフレット □□□)
1982年 第3回 ◯ □
テーマ「COME TOGETHER−今、社会に目を向けて」
プロコンサート スターダスト・レビューほか
講演 中野孝次
ゲスト 斉藤慶子
▽前述の内部資料によると、工学部が正式参加。
.jpeg)
(画像:1983年 第4回六甲祭のポスター 1984年の卒業アルバムから)
1983年 第4回 ◯
テーマ「『大学祭の原点』−今をみつめて」
プロコンサート 大江千里、伊藤さやか
講演 楢崎寛<「神戸からの手紙」編集長>
▽模擬店祭からの脱却、ミーハー的大学祭からの脱皮、統一祭をめざして(医学部・工学部・2課程の正式参加がない)などの問題点が見直される。<『KUBC PRESS』1983年11月号>
▽ポスター画像は1984年の卒業アルバムから。テーマの右肩には、「経済・経営・法・教養・教育・文・理・農・工学部」とクレジットされていて、全学祭へのアプローチを感じさせる。「教養部プレ企画」の文字も見える。
1984年 第5回 ◯
テーマ「六甲のおいしいお祭り〜ダ・セーからの脱却」
プロコンサート 竹中直人、浪花エキスプレス
1985年 第6回 ※
テーマ「夢の見本市~大学生も頭脳を持った」
メインゲスト 本田美奈子
講演 落合信彦、新開陽一
▽1000人程度しか参加できないのにお金がかかるプロコンサートを中止し、無料で参加できる本田美奈子コンサートを開催。室内企画には考古学研究会の「舞子古墳調査報告」や、経済院生協議会主催の新開陽一・阪大教授「国際マクロ経済学の展望」などの企画も。<『KUBC PRESS』1985年11月号>
1986年 第7回 ※
テーマ「はいからさんのはいきんぐ〜脱日常宣言〜」
プロコンサート 島田奈美、松本典子
講演 中島らも
▽一昨年には中止、昨年復活し六月祭と一緒に行われた「芸術祭」(文化総部加盟団体の発表会)が、今年は六甲祭と同時に開催されることになった。自由劇場、はちの巣座は六甲台講堂で、茶華道部、映画研究部などは六甲台第1学舎で公演・展示した。<『KUBC PRESS』1986年11月号>
1987年 第8回 ※
「あなたにとって神戸大学とは」
プロコンサート 長山洋子
講演 竹中平蔵
▽実行委が人気投票を試み、その結果長山洋子の六甲台グラウンドステージ出演が決まった。同時間帯には、六甲台第1学舎102教室で生協組織部クリエイティブスタッフ主催でグラフィックデザイナー・サックス奏者の立花ハジメ講演会も。<『KUBC PRESS』1987年11月号>
.jpg)
(画像:1988年 第9回六甲祭のパンフレット □□)
1988年 第9回 ※
「立ち止まって深呼吸〜となりは何をする人ぞ〜」
プロコンサート 田中律子、つみきみほ&有頂天
講演 近藤勝重<毎日新聞編集委員>(広告研究会主催) ◯
.jpg)
(画像:1989年 第10回六甲祭のパンフレット □□)
1989年 第10回 ※
テーマ「君が戻ってこれる場所」
プロコンサート 遊佐未森とソラミミ楽団※、村井麻里子 ◯
講演 天野祐吉<『広告批評』編集者>※、伊藤光晴<京大教授>※、富岡隆夫<『AERA』編集長> ◯
-.jpg)
(画像:1990年 第11回六甲祭のパンフレット □□)
1990年 第11回 ※
テーマ「Relationship、おすそわけ」※
プロコンサート PINK SAPPHIRE、東京少年
講演 黒田征太郎、佐和隆光<京大教授> ◯
▽六甲台講堂の寄席では、桂枝雀が母校で初めて演じる。桂べかこら弟子も出演。<『KUBC PRESS』1990年11月号>
.jpg)
(画像:1991年 第12回六甲祭のパンフレット □□)
1991年 第12回 ※
テーマ「五臓六腑にしみわたれ!」
プロコンサート 谷村有美
講演 白壁武博<美容形成外科医>
.jpg)
(画像:1992年 第13回六甲祭のパンフレット □□)
1992年 第13回 ※
テーマ「むっ、六甲山が動いた!?―空前絶後の二日間―」
プロコンサート 寺田恵子
講演 太平シロー
1993年 第14回 ※
テーマ「100万ドルの夜景がかすむ日」
プロコンサート 久宝留理子
講演 栗本慎一郎
.jpg)
(画像:1994年 第15回六甲祭のパンフレット □□)
1994年 第15回 ※
「六甲全山大放電~シビレエイとの出会い~」
プロコン 東野純直
講演 ハイヒールりんご、金丸昭久、今里千加子
次回は、震災を乗り越えて開催された1995年の第16回以降の六甲祭について、その歴史をたどります。
○ ○
この連載は、六甲祭実行委員会などの協力を得て、社会科学系学部の同窓会「凌霜会」の機関誌『凌霜』に、2024年1月号から連載されている記事を元に、加筆して転載しています。
▼連載記事リンク
【六甲祭ヒストリー】① 新制・神戸大学「開学記念式典」が戦後の学園祭の出発点
【六甲祭ヒストリー】② 1950年代の「開学記念祭」
【六甲祭ヒストリー】③ 1960年代の呼称は「大学祭」
【六甲祭ヒストリー】④ 1971年〜79年の「六甲台祭」
【六甲祭ヒストリー】⑤ 「六甲台祭」から全学祭への模索
【六甲祭ヒストリー】⑥ 1980年「六甲祭」のスタート
つづく
![]()
コメント
この記事へのトラックバックはありません。














この記事へのコメントはありません。