神戸大の食資源教育研究センターは、鶉野飛行場(姫路海軍航空隊基地)の跡地にある。農場建設時に取り壊されなかった、頑強なコンクリート製の防空壕や機銃座が、終戦から80年経った今も敷地内に残る。ニュースネット取材班は7月、センターの技術員・冨士松雅樹さんに敷地内の戦争遺構を案内してもらった。<久保田一輝、奥田百合子>

(写真:食資源教育研究センターにある防空壕の内部)
※こちらの記事は後編です。前編はこちら↓
【終戦80年】神戸大の食資源教育研究センターに残る戦争の面影(前編)
<食資源教育研究センターに残る戦争遺構>

(センター内戦争遺跡一覧 提供:加西市 *は編集部で追記)
上図は、食資源教育研究センターに残る戦争遺跡の一覧を表している。地図中の番号と説明は以下の通り。
1:爆弾庫
2:防空倉庫
3:機銃座
4:防空倉庫
5:防空倉庫
6:燃料庫入口
7:防空壕
8:防空壕
9:自力発電所(巨大防空壕)
10:円形貯水槽
11:退避豪
12:退避豪
13:駐機場
14:水路
15:円形貯水槽
16:方形貯水槽
17:基壇
18:基壇
①燃料庫入口(地図中6番)

(写真:燃料庫入口)
現在は地中に埋まっているが、燃料庫入口から地下にあった通路を進むと、写真奥に見える池の方向に向かう。この近くでは戦後、不発弾が見つかった。第一発見者は、今回案内してくれた冨士松さんだ。今はもう使われていないが、この場所にはもともと畑があった。冨士松さんが畑をトラクターで耕していると、何か固いものにあたった。これが不発弾の発見の始まりだった。この発見を受けて、センターでは金属探知機による調査が行われた。そして、水田でも新たに不発弾が見つかった。
②防空倉庫(地図中5番)

(写真:現在の防空倉庫跡の入り口)

(写真:防空倉庫の入り口に架けられた梯子)

(写真:防空倉庫の中にある木製の箱)
防空倉庫の入り口は普段、トタンでふさがれている。中には3mほどのハシゴがかけられている。倉庫の中はひんやりと涼しく、真夏でも20度、真冬は10度程度になるという。倉庫の中には大きな木箱が置かれていて、今はサツマイモを貯蔵するのに使われている。冨士松さんは、「昔は足元に水が溜まっていたが、最近は降水量が減ったのか溜まらなくなった」と話す。
③機銃座(地図中3番)

(写真:機銃座の全体)

(写真:崩れたコンクリートブロック)

(写真:機銃座の入り口)

(写真:入り口からは、機銃座の地下部につながる階段がある)

(写真:機銃座の地下部に置かれた棚)
機銃座には戦時中、飛行場や軍事施設に低空から侵入してくる敵戦闘機に対して射撃する、対空用機銃が設置されていた。機銃座は、機銃部と地下部で構成されていて、それぞれは昇降口でつながっている。
機銃座を構成するコンクリートブロックは、一部が崩れていた。大人はかがんで入らないといけない、やや小さな入口から階段を下りると、機銃座の地下部に出る。地下部は円形の空間で、部分的に水が溜まっていた。中に置かれた棚は、戦後に設置されたもので、果樹園で働いていた人々の休憩所や資材置き場として使われていたが、最近は使われていないという。
④防空倉庫(地図中2番)

(写真:防空倉庫の入り口)

(写真:基盤の上に置かれた資材)

(写真:内部にある落書き)
果樹園の中にある、防空倉庫。現在は、資材置き場になっている。倉庫の内部には、黄色と緑の落書きがあるが、いつごろ描かれたかは分からないという。
⑤防空壕(地図中7番、8番)

(写真:防空壕の外観 地図中7番)

(写真:防空壕の外観 地図中8番)

(写真:水が溜まった防空壕の内部 地図中7番)
7番の防空壕には入口が4カ所、8番の防空壕には入口が2カ所あった。入口には普段、動物や人が入らないよう柵がされている。階段を下りて7番の防空壕の中に入ると、内部には50cmほど水が溜まっていた。写真には向かい側の入口が見えているが、その手前に右側に続く通路があった。8番の防空壕も50cmほど水が溜まっていた。
⑥巨大防空壕(地図中9番)

(写真:巨大防空壕)

(写真:粗いコンクリート)
センターの敷地の北西部には、基地内最大の防空壕がある。内部には長さ14.5m、幅5m、高さ5mの空間が広がっている。現在、この場所は加西市が運営する戦時中の飛行場について学ぶシアターになっていて、特別攻撃隊「白鷺(はくろ)隊」の特攻隊員の遺書、手紙を読み上げる映像を視聴することができる。高校生以上は1人500円。土曜日、日曜日、祝日のみに一般開放される。
外側のコンクリートは粗く、冨士松さんは「コンクリートが不足していたので、石でかさましをしていたのではないか」と話す。
⑦円形貯水槽(地図中15番)・方形貯水槽(地図中16番)

(写真:円形貯水槽)

(写真:円形貯水槽の内部、植物が芽を出している)

(写真:円形貯水槽の粗いコンクリート)

(写真:方形貯水槽)
センターの敷地の北西部には、円形貯水槽と方形貯水槽がある。中は埋まっていて、植物が芽を出している。円形貯水槽のコンクリートも、巨大防空壕のものと同様に粗かった。
⑧防空壕(地図中*)

(写真:防空壕)
地図中*で示された地点、巨大防空壕の北側にも防空壕がある。
⑨水路(地図中14番)

(写真:牛舎横の水路)
牛舎横には、姫路海軍航空隊基地当時の水路が残る。センターの東側の水田にある排水路も戦時中のものだという。冨士松さんによると、水田にある方の排水路は戦時中、鶉野飛行場と繋がっていて、人が逃げられるようになっていたという。
⑩円形貯水槽(地図中10番)

(写真:円形貯水槽)

(写真:円形貯水槽の内部)
農舎棟の近くにも円形貯水槽がある。地図中15番の円形貯水槽は土で埋まっていたが、この円形貯水槽は、今もセンターで稲の苗の育苗などに利用されている。
⑪駐機場(地図中13番)

(写真:センター内にはコンクリート製の駐機場がある)
宿泊棟の裏には駐機場(エプロン)がある。冨士松さんによると、この一部は空襲によって壊れたという。進駐軍(GHQ)が戦後の日本の子どもたちにお菓子やお小遣いを渡して、壊すように命じたという話もある。
エプロンの隅には、現在はバスケットゴールが2基置かれていて、センターに所属する学生や、宿泊実習でセンターを訪れる学生が汗を流している。
食資源教育研究センターで研究をしている、農学研究科修士2年の立岩玲さんは、敷地内の遺構について「存在としてはよく知っているんだけど、実情というか深いところまでは知らない。80年前に同じ場所で戦争があったといっても、ちょっと別世界の感じがあるのかな。敷居が高いという気持ちがある」と話した。
敷地内の防空壕の中には、すでに埋められたものもある。畑にして農作業の効率を上げるために、戦後の人々が埋めたという。戦争を経験した人はもうほとんどいない。戦争を知らない世代は、「戦争の記憶」をどうつないでいけばよいのか。薄暗い斜面で草木に覆われていくコンクリートブロックが、80年という月日を象徴していた。

(写真:草木に覆われたコンクリート片)
【取材を終えて】
「戦争遺構」というと、看板が立っていたり、周りが囲われていたりするのかと思った。しかし、食資源教育研究センター内にある防空壕や機銃座は、保存のための手が加えられず残されていることに少し驚いた。鶉野の他にも、神戸大には戦争の痕を垣間見える場所が複数あるが、知らない学生が多いように思う。今年は戦後80年だ。私も個人的に、特定の日や期間だけ、かつての戦争や災害などについて考える自分を恥じる時もある。しかし、だからと言って目を向けないことも違うと思う。戦後80年の今だからこそ、一人の神戸大生として、身近な大学内にある跡地や遺構を糸口にして、80年前の日本を少しでも知ってみたいと思った。<奥田百合子>
取材を通して、経験していないことを伝える難しさを改めて感じた。今回、案内してくれた技術員の冨士松さんも、戦争を経験した世代ではない。私たちは、戦争を経験していない世代から戦争を経験していない世代へ、当時の記憶をつないでいかなければならない。実感が湧かないという学生の声もあったが、実際に防空壕や機銃座の中に入った私も、本当の意味でこの場所で戦争があったという感覚はつかめなかった。内部がやけに奇麗だったことに、どうしても違和感を覚えてしまった。だが、だからといって、戦争を経験していない世代だからといって、何もしなくてよいというわけではないだろう。何か一つでも、当時の記憶をつないでいくことができればと思う。<久保田一輝>
【取材メモ】神戸大学農学研究科 食資源教育研究センターは関係者以外立ち入り禁止。センターから北に1kmほど進むと、「soraかさい」と「鶉野飛行場資料館」があり、鶉野飛行場の歴史について学ぶことができる。
▼関連サイト=soraかさいウェブサイト=https://sorakasai.jp/
▼関連サイト=鶉野飛行場資料館ウェブサイト=https://uzurano.com/
神戸大学・加西市共同研究 鶉野飛行場関係歴史遺産基礎調査「加西・鶉野飛行場跡(旧 姫路海軍航空隊基地)」<2011年3月発行>を参考にして執筆しました。
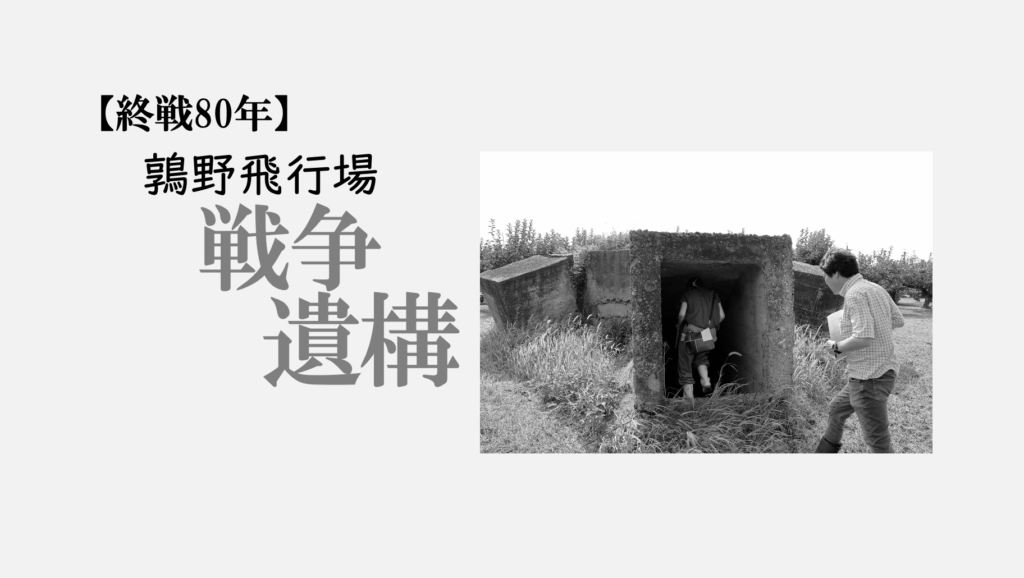
了
![]()
コメント
この記事へのトラックバックはありません。













この記事へのコメントはありません。