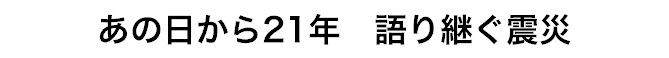
震災知らない世代がイベ主催 みんなで過ごす「5時46分」
2016年1月18日配信 記者=竹内涼
について発表した。ある女子学生は「毎年つどいに行っているが、こういうイベントも新鮮で面白そうだと思った」と話す。その後、参加者はお酒やカフェの料理を楽しみつつ震災の話などで盛り上がった。
主催者の横山玖未子さん(立命館大・3年)は防災関連のサークルで活動している。「つどいに行きたいと以前から友人と話していた。午前5時は一人だとなかなか起きることができないから、時間までを大勢で話しながら過ごそうと考えたのが開催のきっかけ」と語った。フェイスブックなどで参加者を募り、知り合いを中心に災害関連のボランティア経験がある人から、つどいに興味を持ったという人までさまざまな人が集まった。
震災の記憶がない世代が始めた新しいイベントが、恒例行事になりつつある。
夜通し語り合う参加者ら
六甲本通商店街の中にある、学びカフェ「notte」で、16日から17日にかけて「真夜中カフェ ~そうだ、5:46に行こう~」が開催された。16日の夜から集まり、東遊園地で行われる「阪神大震災1.17のつどい」に参加するのがイベントの目的。ことしが2回目の開催で、さまざまな大学から20人以上の学生が参加した。
イベントは自己紹介から始まり、参加のきっかけなど

救援隊「のんびり過ごす会」 東北大からも学生参加
2016年1月17日配信 記者=瀧本善斗
.jpg)
会の模様(撮影=瀧本善斗)
学内のボランティアサークル、学生震災救援隊は16日、「1.17をのんびり過ごす会」を開いた。会場となったサポートステーション灘・つどいの家にはOB・OGや、救援隊の活動に関わる地域の人々が集合。現役部員と鍋を囲み、震災当時を振り返った。
午後7時30分。代表の金川翔太さん(経済・3年)による「献杯」の掛け声で会は静かに始まった。会は、震災直後に行政の支援が行き届かない中で結成された救
援隊が、行政が開く式典とは別に震災を振り返る場を設けたいとの趣旨で始まり、毎年開かれている。しかし金川さんは「救援隊の中でも震災について話す機会は減っている」と風化を実感するという。「普段震災について話さない人が、会では震災当時の記憶を語ってくれる。現役メンバーにとって大事な場」と話す。
救援隊の活動の一つに、被災者が多く住む災害復興住宅などでのお茶会がある。人々のつながりを生むことで高齢者などの孤立を防ぐねらいだ。16日にも神戸市灘区岩屋の復興住宅で開催した。中村茜さん(国文・2年)は「(復興住宅の居住者の中には)今でも震災について話したがらない人も多い。被災者にとって震災は今も続いている」と心のケアの重要性を訴えた。

東北大1年の清水谷苑実さん(撮影=瀧本善斗)
今年の会には、東北大からも1年の清水谷苑実(しみずや・そのみ)さんら学生3人が参加した。3人は、救援隊OBで同大課外・ボランティア活動支援センター特任准教授の藤室玲治さんの下、東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の仮設住宅でお茶会や足湯などの取り組みを行っている。16日に救援隊のお茶会にも参加した清水谷さんは「21年経った今でも震災を風化させないように、街の人々が頑張っているのはすごい」と感心していた。藤室さんは「(東日本大震災の)被災地はこ
れからが肝心だが、世間は収まりを付けようとする。現場に問題がある以上対処していく必要があるということを、神戸の今を見ることで学んでほしい」と期待を示した。
夜通し行われた会の終了後、一同はかつて救援隊が活動した仮設住宅があった大和公園に移動。阪神・淡路大震災の発生時刻、17日午前5時46分に黙祷をした。
若者から「震災の教訓」世界に発信 つどいにブース設置
2016年1月17日配信 記者=有賀光太
神戸市の東遊園地で行われた「阪神大震災1.17のつどい」で、神戸大のKobeRMC(リスク・マネジメント・コミュニティ)が神戸学院大のピース神戸、自治体危機管理研修所と合同で、防災を知り、体験することができるブースを設置した。
ブースでは、パネル展示などで阪神・淡路大震災や東日本大震災、南海トラフ地震について解説し、防災・減災について体験を通じて説明する。KobeRMCは参加者が交流できるコミュニケーションスペースを担当。スタッフが英語を話せるため海外の人でも参加しやすくなっている。他にも、ロープ結索など実際に被災した際に役立つサバイバル術の体験ができるスペースも担当している。
若者を中心として世界に防災意識を広めるため、2013年に日本・韓国・インドネシア人の学生3人がKobeRMCを結成した。現在在籍している約10人のメンバーの中にはセネガル・フィリピン・マレーシアなどさまざまなの国籍の学生も含まれる。つどいに参加するのはことしで3回目だが、実際に体験できるワークショップを開催するのは今回が初めてだ。
メンバーの中村児太郎さん(工・修士課程)は「今回のワークショップなどの活動を通して、マイノリティの人や国籍が違う人など、色んな人が気軽に防災について学べるプラットホームを作っていきたい」と語った。
つどいは震災の犠牲者を追悼することが主な目的として始まったが、震災の教訓を世界に発信し、未来につなごうとする若者が活動する場にもなっている。
ロボット使った救助技術に「竸基弘賞」
2016年1月19日配信 記者=嶋田敬史
左から、亀川哲志氏、広瀬茂男氏、木村哲也氏(撮影=嶋田敬史)
地域人材支援センター(兵庫県神戸市)で今月13日、第11回竸基弘賞授賞式が開催された。竸基弘賞は、阪神淡路大震災で亡くなった竸(きそい)基弘さん=当時(自然科学研究科・博士前期課程)=の名を冠して、国際レスキューシステム研究機構からレスキュー技術に貢献した研究者らに贈られる賞だ。ことしは、岡山大大学院講師の亀川哲志氏、長岡技術科学大専門職大学院准教授の木村哲也氏、東京工業大名誉教授の広瀬茂男氏らが受賞した。
受賞後、3名はそれぞれの研究に対する思いを述べた。
ロボット分野で先端的な研究を続ける広瀬氏は、知的スポーツの導入や人間に代わるロボットの使用範囲など持論を展開した。木村氏はロボットを災害現場で使うための規格とその重要性について、亀川氏は長年研究を続けているヘビ型ロボットについて語った。震災当時高校3年生だった亀川氏は、阪神淡路大震災を知らない世代の学生に対して「君たちが経験した東日本大震災を忘れずに、そこから何をすべきか深く考えて日々勉強をしてほしい」とメッセージを送った。
「ドラえもんのように何でもできるロボットをつくりたい」というのが竸さんの思いだった。そのような平穏な日々のもとにも震災は突然襲ってきた。竸さんの恩師だった松野文俊氏は、竸さんが亡くなったと聞いたときはあまりに唐突で信じることができなかったという。震災の日を振り返り松野氏は、「明日生きているか分からないという事態がある。だから、今日を悔いの無いよう精一杯生きて、人を助けることに貢献してほしい」と、会場に集まった人々へ発した。

光る募金箱 ことしもルミナリエに登場
2015年12月16日配信 記者=瀧本善斗

「光る募金箱」に募金する来場者(11日、神戸市中央区で 撮影=瀧本善斗)
工学研究科塚本・寺田研究室の学生らが、昨年12月4日から13日まで神戸市中央区で開かれた「神戸ルミナリエ」で募金活動に参加した。手製の「光る募金箱」を持ってイベント存続のための寄付を呼び掛け、来場者の関心を集めた。
光る募金箱は、貨幣や紙幣を投入するとセンサーが感知して箱に付けられた発光ダイオード(LED)の色が変化する。暗い場所でも目立つほか、来場者に募金を楽しんでもらうことを意図して同研究室の学生らが製作した。
ことしは、神戸市の木であるサザンカの周りをLEDで形作った蝶が光るものや、「幸せの青い鳥」をモチーフに神戸芸術工科大の学生と共に作ったものなど、5つを新たに製作。過去作品と合わせて10の募金箱が使われた。河田大史さん(工・修士課程)は「来場者の中には震災を知らない世代も多い。募金箱のコンセプトの基本は震災を語り継いでいくこと」と取り組みの意義を説明する。
神戸ルミナリエは阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼するなどの目的で1995年から毎年開催されている。数々のイルミネーションで街を彩る冬の神戸の風物詩だが、活動資金が慢性的に不足。2007年から来場者に一人100円の募金をよびかけ存続を図っている。同研究室でも募金活動の開始当初から、光る募金箱を毎年製作しボランティアにも加わってきた。
学生らは期間中毎日、会場に立ち寄付を呼び掛けた。子どもが募金箱に駆け寄って興味深く見つめる姿や、来場者が色の変化に感嘆する様子が見られた。島根県から訪れたという夫婦は「ルミナリエのイルミネーションともマッチして素敵だと思う」と上機嫌。3つの箱に募金し、写真も撮るほど気に入ったようだった。河田さんは「毎年新作を楽しみに来てくれる人もいる。来年以降も取り組みを続けていければ」と話している。
Ⓒ 2016 神戸大学ニュースネット委員会