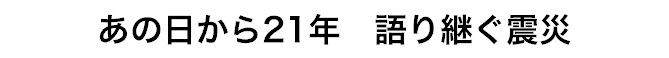
災禍 神戸大生も直面 阪神・淡路大震災から21年
2016年1月14日配信 記者=坂本知奈美・瀧本善斗
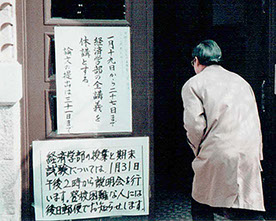
六甲台本館に張り出された経済学部の休講通知(1995年1月27日 ニュースネット委員会所蔵)
阪神・淡路大震災の発生から17日で21年となる。震災では神戸大にも学生や教職員など計50人の犠牲が出た(旧神戸商船大=現海洋政策科学部=含む)。大学には、家を失った大勢の近隣住民が避難。キャンパスも日常を失う災禍を前に、神戸大生の中には被災調査やボランティア活動に取り組む人もいた。
◇大学は避難所に 期末試験は中止
農・工の両学部は神戸市から緊急避難場所に指定されていた。地震直後、両学部だけでなく国際文化・発達科学などの学部にも避難者が押し寄せ、急きょ受け入れることになった。
六甲台グラウンドや発達科学部グラウンドには、20日から自衛隊がキャンプを張った。当時国際文化学部2年の伊藤耕二さんは、自衛隊が炊き出しや仮設風呂の提供を行う姿が印象深いと話す。「設備が整っていてすごいと思った。感謝している人も多いのでは」
混乱の中、授業は1995年1月29日(日)まで全学で休講。その後も授業や期末試験は原則として中止され、単位認定は平常点やレポートにより行われた。
卒業論文は、期限こそ延長されたが提出は求められた。地震で家を失った、当時工学部4年の藤江徹(いたる)さんは「この状況でも卒論を書かせるのか」と怒りを覚えたという。
◇工学部生も奔走 被災調査の使命
工学部の学生の中には、建物の被害状況の調査に加わった人もいる。
藤江さんも神戸市や芦屋市などで調査に当たった。「(地震で)
発達科学部グラウンドにキャンプを張った自衛隊(1995年2月8日 ニュースネット委員会所蔵)
自分の家も無くなったのになんで他人の家調べてんねん」という悔しさはあった。しかし「やるしかない」と、大学院進学後も半年ほど調査に関わり続けた。
当時同学部4年の越山健治さんは、火災が起きた場所で住民に聞き取りを行った。「今しか聞けない(当時の)状況を残さないといけない」という心境だった。衝撃的な状況を前に「使命感が無ければ(現場の)写真は撮れなかった」と当時を振り返る。
越山さんは現在も、関西大准教授として、都市防災の研究を続けている。
◇「恩返ししたい」学生震災救援隊
23日には神戸大生の有志が「学生震災救援隊」を結成。伊藤さんも2月から参加した。きっかけは地震当夜の避難所で見ず知らずの人からおにぎりをもらったこと。「なんとか恩返しをしたい」と考えた。
伊藤さんらは、灘駅前で鉄道利用客向けに休憩所を運営した。当時JR神戸線は灘駅から住吉駅までの間で不通となり、代替バスが運行され、灘駅が人々の移動の拠点になっていた。休憩所では軽食を提供したり、利用者と雑談したりして、被災した街を和ませた。
4月頃からは、仮設住宅に入居する高齢者が孤立しないように、お茶会を開くなどの活動も始めた。今も救援隊が続ける取り組みの一つだ。伊藤さんは「神戸大生が地元の人と関わるきっかけになった。今でも活動が続いているのはすごい」と感慨深く語った。

職員の姿「情に堪えず」 学長、定年直前も震災対応
2016年1月14日配信 記者=瀧本善斗
当時学長だった鈴木正裕さん(法学部名誉教授)は、地震発生から4日目に大学で電話を受ける。個人的に親しかった応援団OBからの「団長の高見秀樹君=当時(経済・3年)=が亡くなりました。葬式に花を出してください」という内容。鈴木さんに神戸大生の死亡情報が入るのは初めてだった。「応援団長をやるくらい体格のしっかりした学生が亡くなった。今後も死者が出ると予感した」と話す。
職員は避難してきた近隣住民の対応にも追われた。神戸市から届けられた物資を、避難者がいる各所に運ぶのも職員の仕事。鈴木さんは「職員にも被災者は多い。日に日に痩せ、ひげも伸びる。情に堪えない思いをした」と唇をかんだ。
週に1度しか帰宅せず、連日泊まり込みで勤務してきた鈴木さんは地震から約1カ月後の2月15日に定年退官。久しぶりに帰宅すると妻から、前夜に鈴木さんの母が亡くなったことを伝えられた。危篤の
鈴木正裕元学長(2015年12月25日・大阪市北区で 撮影=瀧本善斗)
時、鈴木さんは大学で慰労のすき焼きパーティーを身近な職員と開いていた。妻は秘書役の職員に電話を入れたが、戻っても間に合わないと考え「(知らせなくて)結構です」と伝えていたという。
奔走の日々を振り返り鈴木さんは訴える。「神戸大は歴史に残る震災を経験した大学。学生も教職員も過去に敏感であってほしい」

「語り継ぐべき」9割超える 本紙学生アンケート
2016年1月14日配信 記者=竹内涼
ニュースネット委員会では関西の現役大学生203人にアンケートを実施し、阪神・淡路大震災に対する学生の意識を調査した。
「震災について家族や友人と話すことはありますか」という問いに対し、「あまり話さない」、「全く話さない」と回答した人は55.2%に上った。戦後最大級の大型地震でも、語られる機会が少ない現状が浮き彫りとなった。
44人の学生が亡くなるなど、大きな被害を受けた神戸大。しかし現在神戸大に通う学生の15.0%が1月17日を震災が起きた日だと知らなかった。
「これまでに被災者から当時の話を聞くことはありましたか」という問いに43.3%の人が「はい」と回答した。震災を経験した家族から話を聞いたり、学校で被災者の講演を聞いたりした人が多かった。今の学生が当時の状況を知る際に、被災者の話は重要な手掛かりとなっている。
20年以上たった今でも「震災はこれからも語り継ぐべきだと思いますか」という問いには、9割以上の学生が「とても思う」、「まあまあ思う」と回答した。「学校教育で地震の怖さをもっと語り継ぐべき」、「周りで少しでも(震災を語り継ぐための)活動があれば」という意見もあり、風化させてはいけないという意識を持つ学生が多かった。
大学や出身地にかかわらず多かったのが、震災を身近に感じられないという意見。震災当時の記憶がある学生がほとんどいない中、震災の教訓を伝える重要性は高まっている。

Ⓒ 2016 神戸大学ニュースネット委員会