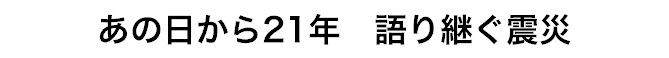
略称凡例 ▽NN=ニュースネット委員会
▽震災の記録=『兵庫県南部地震による震災の記録』(神戸大庶務部庶務課・編、1996年1月)
「震災タイムドキュメント」トップに戻る
1日
2日
3日
7日
8日
9日
10日
11日
13日
15日
17日
18日
20日
23日
26日
27日
28日
95年度入試の出願期限。郵便事情の悪い1月27日の中間集計で志願者減と報じられた影響か、その後志願者数が増加。最終的には前年度比約3000人となった(産経新聞1995年2月1日記事より)。
国際文化学部の水道が復旧(震災の記録15ページ)。
農学部の水道が復旧(震災の記録15ページ)。
理学部の水道が復旧(震災の記録15ページ)。
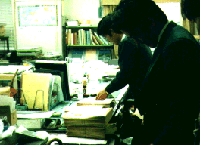
願書が届く法学部(1月27日 NN)
「神戸大学学生ボランティア」の団体設立届を受理。3月31日までの期間、51人で結成された(震災の記録15ページ)。
鈴木正裕学長(当時)が「神戸大学構成員の皆さんへ」と題する声明。「教職員・学生諸君の多くが、自ら被害を受けながら(略)救援と復興に献身的な活躍をされていることに感謝しております」などとする内容(震災の記録116ページ)。
国際・教養系図書室(現総合・国際文化学図書館)を除き、学内の各図書館で書庫の整理がほぼ完了した。3日までにすべての図書館で再び開館するようにはなっていたが、書庫は整理が済んでいなかった(震災の記録14~16ページ)。
部局長会議が開催され、95年度の授業開始日を4月10日に決定(震災の記録17ページ)。
被災学生を学生寮に緊急受け入れ。入寮期限は3月20日までで、20人の申し込みがあったという。また前期入試に向けて志願者に受験票などが発送された。(震災の記録17ページ)。
阪神本線では青木~御影間が復旧し、御影から大阪方面は復旧した。神戸方面が復旧するまでには6月26日を待たなければならなかった(震災の記録47ページ)。
学生部が各学部などに被災学生の94年度未納授業料について聴衆を猶予するよう依頼。申請した院生3人、学部等生10人の全員が猶予を許可された(震災の記録73ページ)。
被災した入学志願者を対象とする「特例入試」の概要を発表。被災地に住居や高校などがあり、他の国公立大に合格していない、などの条件を満たした志願者が対象。全学部で27人が募集されることになった。(震災の記録18、79ページ)

震災1カ月。95年卒業予定者の、全学共通授業科目のレポート提出締め切り日(震災の記録64ページ)。
鈴木正裕氏(1月20日 NN)
京都大防災研究所が余震観測を行うための場所として住吉寮を3月4日まで提供。3台の地震計が設置された。(震災の記録19ページ)
大阪ガスが灘区・東灘区でガス復旧工事を行うための資材置き場として六甲台グラウンドを使用開始(震災の記録19ページ)。
全学共通授業科目委員会が実施された。鶴甲第1キャンパスが避難所として使われる中、95年度の健康・スポーツ科学自習は発達科学部体育館や六甲台グラウンドなどを利用することに決まった。(震災の記録20ページ)
教官有志が専門分野を越えて研究・交流を進める「阪神・淡路大震災の発生、被災、復興と防災にかんする総合的研究会(神戸大学)」(略称=神大震災研究会)をスタート。(NN[リンク])
前期入試が実施された。震災前の予定より1日遅らせ、上槻間の麻痺を考慮して大阪大や岡山大にも会場を分散させる異例の措置をとった。(NN[リンク])
農学部の避難所で避難者代表から、多数の外国人留学生が避難所用の公衆電話を深夜に使い声高に話すことについて苦情が寄せられた。農学部は英文の注意書を作成し掲示したという。(震災の記録21ページ)
震災を理由に企業から採用内定の取り消しを受けた学生に対する新規募集申し出がこの日までに14社あった。(震災の記録21ページ)
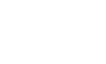
「震災タイムドキュメント」トップに戻る
Ⓒ 2016 神戸大学ニュースネット委員会