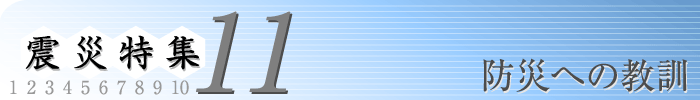インタビュー 〜関学災害復興制度研究所・山中茂樹さん
関学は震災10年を迎えた2005年1月17日、災害に遭った人々の生活や地域の「復興」を支援する「制度」を研究対象とする「災害復興制度研究所」を新設した。開設から1年、同研究所主任研究員の山中茂樹教授に話を聞いた。
―研究所設立の経緯は?
被災地西宮に本拠を持ち、学生・教職員23人が犠牲になった大学として、大災害後に待ち受ける被災者の生活と地域の復興という公的課題に貢献したい、という思いからです。
―どのような研究をしているのですか?
「災害大国」「地震列島」といわれる日本では、自然災害で被災した場合、自力復興が原則です。私たちは災害に遭った人々の生活や地域の「復興」を支援する制度を研究対象にしています。しかし、復興の定義は人それぞれによって違うものです。例えば、福岡西方沖地震で被災された玄界島の人に、どういった状態が復興かと尋ねると、こうおっしゃいました。「あの山の斜面に地震の前と同じように灯がついたら」と。戦後の成長社会下で作られた現行の災害法制は被災者の応急救助や道路・橋などのインフラ復旧を主眼としていて、人々の生活や地域の長期にわたる「復興」に正面から取り組んでいなかった。研究所では、被災実態と現行の復興制度について研究をし2010年をめどに人々の生活や地域の視点に立った「災害復興基本法」の提案を目指します。
―阪神・淡路大震災後の復興の過程で問題になったのは?
はい、大きく2つありました。街の再建は住まいの再建です。しかし、このことに対する有効な手段がなかったのが1つ。例えば神戸では災害復興住宅が不便な所に建てられ、今では住人が超高齢化している。
もう1つは住まい・コミュニティー・生業の三位一体の再建が十分でなかったこと。生業に関してはお金を貸すだけ。商業に対する支援がなかった。
―阪神・淡路大震災の教訓は生かされていますか?
例えば仮設住宅。神戸では入居が抽選で行われたために、せっかくの隣近所の付き合いが生かされなかった。コミュニティーがなくなったことによる高齢者の「孤独死」も多かった。このことを教訓に、新潟では仮設住宅への入居は地区毎に行われました。制度や法が定められていたわけではないが、経験から学んだことが生かされた結果です。
―今後の活動予定をお聞かせください。
昨年は神戸、旧山古志村、三宅島等に行き、被災地の復興状況を現地調査をしました。今までの活動を冊子にまとめ、朝日新聞と共同で災害復興制度に関する調査も行いました。
今後は、旧山古志村の追跡調査、復興ファンドの研究、自治体調査などをやっていかなければなりませんね。また、予想される東海・東南海地震が発生した場合、現行のプランと研究所が提案する新たなプランと、どちらが安価な予算で復興を進められるのか、検証を行いたい。そして我々の提案する復興の理念を具体的な制度に落としこんでいきたいですね。
震災特集2006 各大学の防災への取り組み
過去の震災特集
2004年
『大学から震災の灯は消えたか』特別版
2003年5月〜11月
【緊急連載】『大学から震災の灯は消えたか』
2003年
『体験者として伝える事』
2002年
『震災7年目の学生たち』
2001年
『覚えていますか あの日のことを』
2000年
『被災学生 5年目の追悼手記』
1999年
『震災グラフ 大学から1999』
1998年
『いま、後輩たちに伝えたいこと』
1997年
『被災下宿は今』