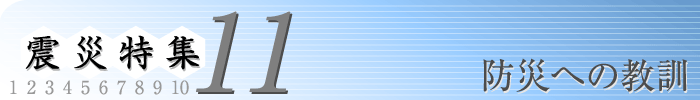神戸大学
海洋政策科学部(旧神戸商船大)関係者を含め、44人が犠牲となった神戸大。震災当時、大学の体育館は被災者のための避難所として活用された。あれから11年。大学は震災の教訓をどのように生かしているのだろうか。
医学、土木工学、社会科学など多方面から研究を進める同大学は、阪神・淡路大震災で得た教訓を国内外で還元している。昨年1月には、スマトラ沖地震の被災地インドネシアに医学部の医師を派遣し、復興活動に貢献した。
新年度は、新たな取り組みとして全国の大学で初めて、学部を横断した災害援助組織を設立する。この組織は、神戸大が震災を教訓に設立した「都市安全研究センター」内に設置される。同センターによると、大きな災害が起こった場合には、被災地に向かいどのような援助が可能なのか調査。専門家らが、それまでの研究結果をもとに復興のノウハウを伝える。
阪神・淡路大震災では学内の施設1棟が中破。被災後に建て直しを行い、施設の改修を進めた。学内の施設では、1981年以降に建てられたものは、全て耐震基準を満たしている。
 1万7000人以上の学生(2005年度現在)を擁するため、全学的な避難訓練を行うことは難しい。同大学は、施設の耐震化と合わせ、学生全員に防災マニュアルを周知させることで、万一の事態に備える。
1万7000人以上の学生(2005年度現在)を擁するため、全学的な避難訓練を行うことは難しい。同大学は、施設の耐震化と合わせ、学生全員に防災マニュアルを周知させることで、万一の事態に備える。
一方で、神戸大の学生寮は、国維寮と住吉寮(国際学生宿舎以外)で現行の耐震基準を満たしていないことがわかった。震災で大きな被害はなかったものの、寮生には施設の安全性に不安が残る。住吉寮国際学生宿舎に住む学生(発達・2年)は「(学生寮で)まだ耐震化されていないものがあったことに驚いた。自分に直接関係ないとはいえ、寮生のためにもできるだけ早く工事してほしい」と話す。大学側は「概算要求を行い、順次改修したい」としている。
震災特集2006 各大学の防災への取り組み
過去の震災特集
2004年
『大学から震災の灯は消えたか』特別版
2003年5月〜11月
【緊急連載】『大学から震災の灯は消えたか』
2003年
『体験者として伝える事』
2002年
『震災7年目の学生たち』
2001年
『覚えていますか あの日のことを』
2000年
『被災学生 5年目の追悼手記』
1999年
『震災グラフ 大学から1999』
1998年
『いま、後輩たちに伝えたいこと』
1997年
『被災下宿は今』